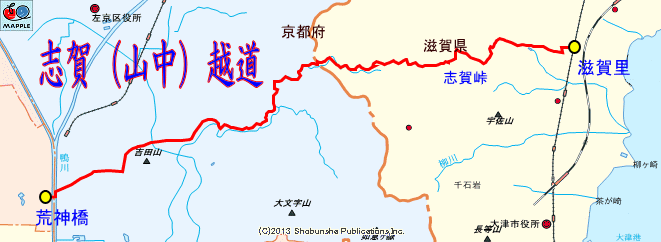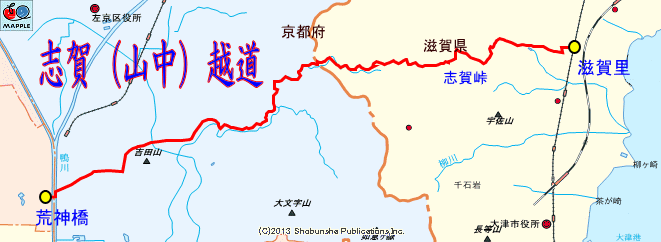志賀(山中)越道
平安時代、京都から琵琶湖方面へ行こうと思うと
1 京三条から日ノ岡峠、逢坂の関を越えて大津へ至る道
2 北白川から、山中町を通り、志賀峠を越え滋賀里へ至る道があった。現在この道は途中で府道、
県道30号線と合流し、通称、山中越と呼ばれている。
30号線はそのまま大津京へ抜けているが、志賀越道は、途中の山中町より旧道へ入り、志賀峠を
越え、かって存在した崇福寺を通って滋賀里へ至る。京都から坂本や北陸道へ繋がる道として良く
使われていた。今回ここを歩いて見ました。
参考書「京の古道を歩く 増田 潔 」。
「京都の地名検証3 京都地名研究会」
志賀峠付近は/25000の地図にも道の記入が無く、現地の標識に従いました。 |