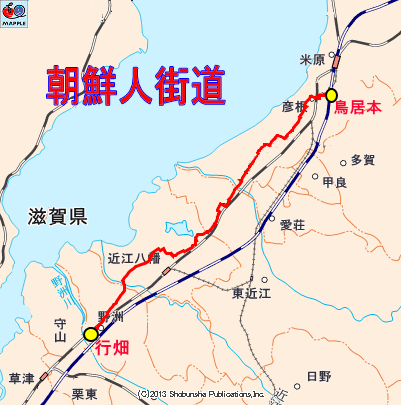 朝鮮人街道 朝鮮人街道
朝鮮人街道とは、滋賀県野洲市行畑で中山道から分岐し、琵琶湖東岸を北上し、彦根市鳥居本で再び中山道に合流する約41kmの街道です。元々琵琶湖舟運の港を繋ぐ、陸路として便利だった道を、信長が幹線道路として整備し、その後、関ヶ原の戦いで勝利をおさめた家康が凱旋した時に通ったという、めでたい道として、将軍上洛や外交使節の通行の際にのみ使われた。 鎖国時代、唯一の外交関係があった、朝鮮からの外交使節が通ったので、この朝鮮人街道の名前がついた。
朝鮮通信使について
この場合、通信とは情報を交換するという意味ではなく、「信(よしみ)を通ずる」の意味で、親善友好使節団のことである。使節団の一行は正使、副使のほか、軍人、書記、医者、学者、画家、書家、薬師、曲芸師などで編成され、約400人に及んだ。太鼓などを打ち鳴らし、楽器を演奏しながら、曲芸を見せながら華やかに賑やかに、進んだといわれる |
参考書
「歴史の道調査報告書 朝鮮人街道」(滋賀県教育委員会) |