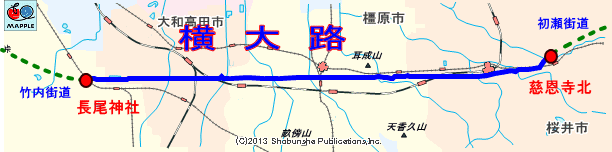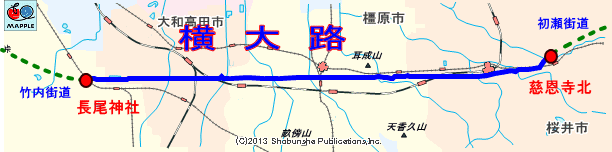■尺土~髙田川
すぐ先は「尺土」という町。もともと赤い土が出たので赤土といったのを、字の良い尺土と変えたと伝えられる。尺土駅前に●春日神社がある。尺土の氏神。祭神は天児屋根命で、社殿内には大絵馬が掛けられているが、扉に鍵が掛って覘くだけで撮影ができなかった。 国道168を東にとって行くと●髙田川。春には桜がきれいだろうと思う。左岸には大中公園が広がっている。園内の一角に●静御前の記念碑が建っている。いうまでもなく源義経の愛妾である。この説明では吉野で義経と別れ、途中で捕らえられて、鎌倉の頼朝の前で舞を踊ることになるが、許されて大和に帰り、ここ母親の「磯禅師」の里でおわるとある。街道の南側の「磯野」の町は静御前の母親「磯禅師」の故郷といわれて、御前にまつわる史跡があちこちにある。墓も探して見たけどよくわからなかった。日光街道を歩いたとき、栗橋駅の前に静御前の墓というを見ており、伝説なのでどちらがどうともなかなか難しい。
静の遺跡を探して、髙田駅の回りをうろついてしまったが、ほとんどわからなかった。 10:35 |