川越街道
戦国の世、太田道灌は古河公方に対する防衛として、江戸城、川越城を築いた。その際江戸、川越間の古道をつなぎ合せて一本の道を通した。 この道が川越街道の始りとされ、江戸時代に入り、川越藩の松平信綱によって、中山道の脇街道として整備されたのが脇街道としての川越街道である。中山道を板橋宿で分岐し、上板橋宿、下練馬宿、白子宿、膝折宿、大和田宿、大井宿の各宿が置かれた。 川越は江戸の北西の守り地としても幕府も重視しており、松平信綱をはじめ老中級を川越城主として送っている。江戸時代の中期ごろには、新河岸(しんがし)川の舟運の便もひらけ、江戸と川越はいっそう密接なつながりをもつようになった。「川越」の街は「小江戸」などと呼ばれ、土蔵造りの家や、「時の鐘」は、「小江戸」の面影をよく伝える。川越までの距離は名産のさつまいもを使い「九里(栗)よりうまい十三里半」とか宣伝されたが、実際は11里程で、板橋からの9里弱(34km)を3回に分け歩いた。
参考資料・・・・・「川越街道」(笹沼正巳外著、)
「歴史の道調査報告書」(埼玉県教委)
「川越街道展 板橋区郷土資料館」など |
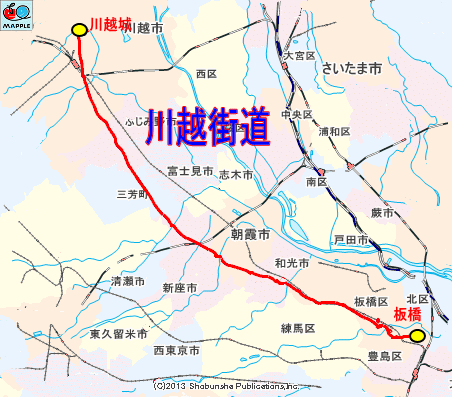 |