日光壬生道
日光街道(道中)を小山の喜沢の追分で分岐し、壬生、楡木、鹿沼、文挾、などを経由して今市で再び日光街道と合流する道です。小山宿から今市宿まで12里27町(約50km)と、日光街道より1里10町(5km)ほど短くてすむことから日光に行く人には大いに利用されていました。慶安4年(1651)に亡くなった三代将軍徳川家光の遺骸を江戸から日光に改葬するときはこの壬生道を通ったこともあって、道中奉行の管轄下に置かれるようになった。公式の将軍の日光社参は、往路は日光街道を使用し、帰路はこの壬生道を通ったという。そして日光街道の西を通ることから日光西街道とも呼ばれた。 宿場は 飯塚、壬生、楡木、奈佐原、鹿沼、文挟、板橋の7宿あった。
(小山、今市を除く)
参考資料
「今昔三道中独案内ー日光.奥州.甲州ー」(今井金吾著 日本交通公社
「街道マップ日光例幣使道・日光壬生道」(五街道ウォーク事務局
発行)の巻紙の形をした地図を購入しました。 |
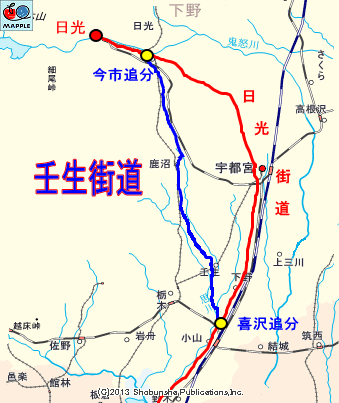 |