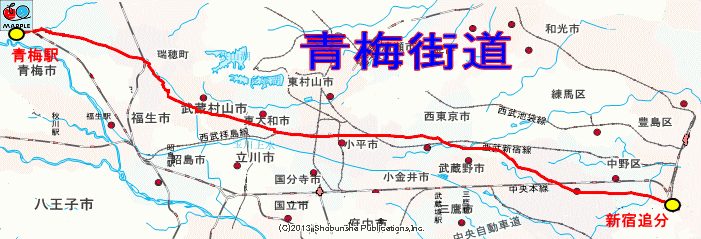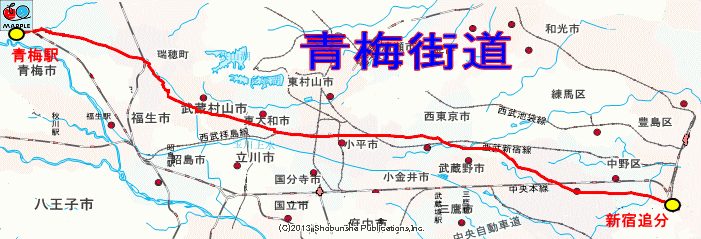青梅街道
家康の江戸入城後、江戸城の大改修に当たって、白壁用の石灰が大量に必要となったため、青梅の成木村で採れる石灰を運搬する道路として、大久保長安の指揮の下に整備された脇街道です。当時の名称は成木街道と呼ばれた。街道は内藤新宿で甲州街道から分かれ、青梅、大菩薩峠を経由し、甲府の東にある酒折村(現:甲府市酒折)で甲州街道と再び合流する。このため、「甲州裏街道」とも呼ばれた。距離で甲州街道より2里短く関所が無いため、庶民の旅客にも多く利用された。宿駅として中野、田無、小川、箱根ヶ崎があった。
青梅から先は山道でもあり、交通不便の為、当面新宿追分から青梅まで扱っておきたい。距離約11里(43km) |