佐屋街道
東海道は宮の宿から桑名までは木曽川など大河が流れ渡川が困難なので宮から海路「七里の渡し」が採用された。
しかし天候による欠航や、船酔い、特に女性が舟を嫌うなどにより、熱田より陸路を西へ進み、岩塚、万場、神守、佐屋と四つの宿場を経て、木曽川を3里下り、桑名へ至る「佐屋廻り」と呼ばれる方法も多く利用されました。
この道は既に江戸時代以前から存在していたが、特に三代将軍家光が上洛の折利用したこともあり御殿や伝馬所等が整備され、東海道の主要脇往還として道中奉行の管轄下になり、一里塚や宿場も整備されました。佐屋川自体は、明治以後の木曽川改修により埋め立てられてしまいました。
2008年8月3,4日の宮宿まで達した後、ついでに歩きました。 24.1km程度でした。 |
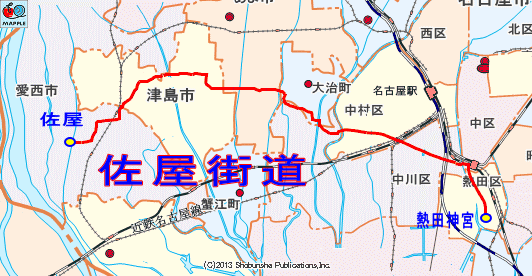 |