武蔵国は、知々夫国造、无邪志国造、胸刺国造という3つの国造を合せ6世紀に成立したとされる。現在の埼玉県、東京都、神奈川県の一部が相当する。当初東山道に属し、上野国から連絡道を南下し、また下野国へ北上していたが、宝亀2年(771)に東海道に属することになった。
郡の数は秩父郡外21郡を数える。武蔵国府からそれぞれの郡への連絡道があったと考えられ、ここでは足立郡衙が付近にあったと考えられる、大宮市氷川神社まで歩いて見た。途中乗瀦駅(あまぬま)(杉並区清水3丁目付近)を通過し、前半は人見街道、浦和から近世の中山道に合流します。
参考資料
「武蔵古道・ロマンの旅」 (芳賀善次郎)
「府中市史 杉並区史、」外 |
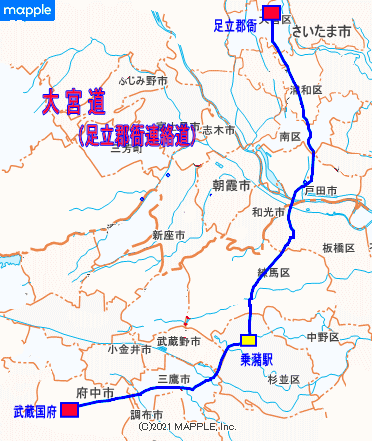 |