西近江路
西近江路(にしおうみじ)は、近江国(滋賀県)から越前国(福井県)へ通じる北陸道を指し、交易上重要な街道であった。人々の往来が多いだけでなく、壬申の乱、藤原仲麻呂の乱、源平合戦、織田信長の朝倉攻めなどでは大軍がこの道を移動している。また、平安時代の遣渤海使もこの道を通 って都へ向っていた。
近世の北陸道は西近江路、北国海道、北国道 などとも呼ばれた。
起点は大津の札の辻であり、琵琶湖岸を北上し 海津町へ向い、海津から七里半越えを経て敦賀へと通じていた。
宿場は衣川(堅田)、今宿(志賀)、木戸、北小松、河原市(新旭)、今津、海津の7宿。距離は海津町まで68km程度である。
参考資料
歴史の道調査報告書 西近江路 (滋賀県教育委員会) |
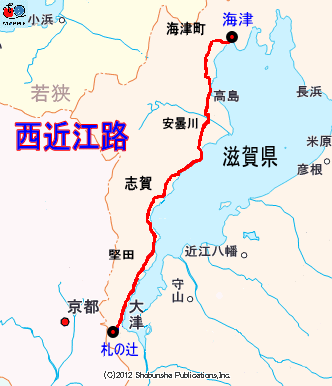 |