鎌倉街道
鎌倉街道」とは、鎌倉時代に幕府のある鎌倉と各地を結んだ道路網で、鎌倉幕府の御家人が有事の際に「いざ鎌倉」と鎌倉へ馳せ参じた道である。
各地から鎌倉を結ぶ街道は関東地方に限らず、ほとんどが鎌倉街道と呼ばれたという。街道は古代の官道や地方道を繋いだり、不足部分は幕府自体が建設したりして造られた。江戸時代に五街道を始め街道が整備されると、その役割を終えたが、中世から江戸期にかけて政治的、文化的に果たした役割は大きい。
鎌倉街道と称される枝道などは数多くあるが、主要な道としては下記の3本
の道がある。
上道・・鎌倉から化粧坂を越え、武蔵西部を経て高崎に至り、信濃、越後
へ抜ける古道。
中道・・鎌倉から巨福呂坂を通り、武蔵国東部を経て下野国から奥州へ至る。
下道・・鎌倉から朝夷奈切通を越え、武蔵国東側の東京湾沿いを北上して
常陸へ抜ける。
今回は中道に続き、下道を歩いた。ゴ-ルの目途は松戸
参考資料
「中世を歩く(東京都その近郊に古道・鎌倉街道を探る)」 北倉庄一
「旧鎌倉街道探索の旅 下道遍」 芳賀善次郎 |
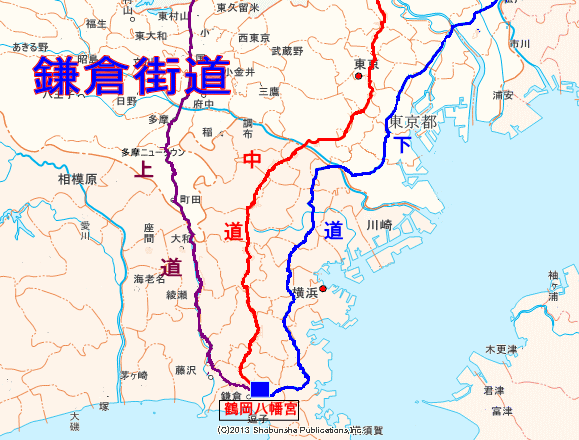 |