下妻街道
中川の自然堤防上に築かれた古道である。その起源は平安時代の「奥州古道」 にさかのぼるといわれ、前九年の役(1051~)、後三年の役(1083~)の際安部時頼の討伐に向かう源頼義、義家らの軍勢が通ったという。
その後、近世に入ると、日光道中と水戸街道の中間に位置し、茨城県下妻方面への街道として大いに利用された。
千住宿で水戸街道と日光街道とに分かれ、吉川、水海道、下妻、を経由。さらに北上して喜連川宿で奥州街道と合流する。 約150km
但し下妻道は流山から下妻へ向かう道など地方により色々呼ばれて場合もある。
参考図書は少ないが
「足立区史」、「吉川市史」、「新編武蔵風土記稿」
外に色々なhpを参照しました。
|
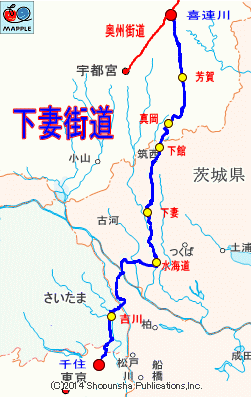 |