
中 山 道
|
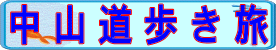 |
4 大宮宿から上尾 歩行地図 |
| 大宮宿入口-北大宮-宮原-馬喰新田-上尾仲町 9.7 km |
|
4 大宮宿
武蔵国第一の宮である氷川神社があるので大宮という。宿の規模は、浦和宿、上尾宿よりやや大きい宿場であった。。脇本陣9軒は中山道69次の中で最高の軒数である。本陣は臼倉新右衛門がつとめていたが、文政期以降山崎喜左衛門がつとめた。現在高島屋が建っている場所は、大宮宿の草分け、寿能城家老北沢家の屋敷跡である。同家は紀州候の鳥見役として御鷹場本陣と宿駅の脇本陣と兼ねた。
本陣1、脇本陣9、旅籠25、 |
  ●再訪 2006.10.21 ●再訪 2006.10.21
本来の大宮宿を再訪した。一の鳥居の所まで戻り、大宮宿を歩くこととした。現在大宮駅前の道は平成19年度に電柱を撤去するとのことで、いたる所工事中であった。歩道もガタガタで歩きにくかった。
●鳥居前の道標
中山道も旅人が増えたので、寛永5年(1626)幕府は関東郡代伊奈忠治に命じ、鳥居からまっすぐ土手町へ通じる道を作らせこれを中山道とした、ここから氷川神社の池の裏を斜め左からくる旧中山道との合流地点までを大宮宿とした。この道標には右氷川神社、左中山道と刻まれている。現在の道は交通の要路で旧道の面影は全くない。案内看板も見あたらない。問屋場とか高札場とかくらい案内板立ててもよいと思う。
14:28 |
 ●商人宿の看板 ●商人宿の看板
すぐに右手に商人宿という看板が立っていた。こういうのが宿場らしいところで、旧家だと面白いのであるけれど、普通の民宿風の大きめの家であった。人がいたので写真は撮らず。
|
  ●塩地蔵 ●塩地蔵
吉敷1丁目右手、ビルの奥に塩地蔵が寂しく建っている。案内板も道に出てないので見過ごしやすい。江戸時代娘二人を連れた浪人が大宮宿で病を得た際、娘の枕元に地蔵が立ち、塩断ちをすれば回復すると告げたことから、娘達は早速塩断ちし、地蔵に祈ったら治癒したという伝説によっている。江戸時代から線香と塩を供える慣わしになっているそうで、右側の地蔵は新しいものなので塩をあげないでくださいとある 14:40 |
  ●旧家 ●旧家
街道左側に旧家らしき建物、2棟建っている。
●本陣跡
大宮駅前からはいるすずらん通り中程に、旅籠屋次郎という食べ物屋さんがあり、そこが本陣跡という案内が立っている。 15:23 |
 ●東光寺 ●東光寺
本陣跡をすぎて大宮小と並んで東光寺という大きな寺があるのだが、現在庫裏建設中ということで、ゆっくり見物どころでなく、一応萬霊塔というのをを撮っておいた。寺伝によると、もとはこの地ではなく、大宮黒塚(氷川神社の東方)にあり、平安末期(約八百年前)武蔵坊弁慶の師匠、山城国京都鞍馬寺の東光坊阿闍梨宥慶法印が黒塚の鬼婆々を法力をもって退散させ、鬼婆々に殺された人々を葬る為に、この地に庵を結び天台宗寺院として開創されたのに始まる・・・・。 この鬼婆というのが有名な福島県安達太郎山の「安達ヶ原の鬼婆」のことで、安達ヶ原の方はみちのくの話だが大宮の堀之内を昔は足立原と言っていたらしく、混同したらしいがこっちの方が正しいらしい。 ちなみに新編武蔵風土記稿にはこうある・・・・「東光寺 大宮山と号す。曹洞宗新染谷村常泉寺末なり、寺記及鐘銘によるに、当寺は昔紀伊国熊野那智山光明房の住侶、宥慶阿闍梨関東下向の時、当国足立原に宿りて黒塚の悪鬼を呪伏し、その側に坊舎を立て東光坊と号す。是れ熊野の光明東国に輝くと云ふ意を表せしとなり。今按に此説いと浮きたる事なり。想ふに此所に黒塚と云塚ある故に、彼の平兼盛が陸奥の安達原の鬼を詠ぜし歌に附会せしならん。 |
 さて旧中山道と合流し道を進める。JR東北線を潜り、宮原駅前をすぎる。●加茂神社 さて旧中山道と合流し道を進める。JR東北線を潜り、宮原駅前をすぎる。●加茂神社
英泉の木曽街道の絵に描かれて有名な神社。今は幟もなく静かな神社である。京都上賀茂神社を勧請したと伝わる加茂宮村の鎮守。この先はどうというわけでなく淡々と歩いてゆく。途中宮原図書館で小休止。
その後行くと宿に入るお定まりで少しカーブしてJR上尾駅前。上尾宿になる。 |
|