
中 山 道
|
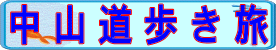 |
41 三留野宿から妻籠宿へ 歩行地図 |
| 三留野宿-和合-神戸-せん沢-妻籠 4.7km |
|
41三留野宿
宿の名前は中世に木曽氏の館があって「御殿(みどの)」と呼ばれたことに由来しているといわれている。ここは万治元年(1658)から宝永元年(1704)まで約50年間ほどで4回も宿のほとんどが焼失するような大火にあい、特に疲弊度が大きかった。また明治14年の大火で宿は全焼し、現在ある建物はそれ以降のものとなっている。宿は新町、上仲町、下仲町坂の下、と続き、長さは2町15間であった。
三留野付近は高い山々が木曽川べりまで迫っていて、大雨ともなると「蛇抜け」と呼ばれる土石流が起こり交通の難所となっていた。
本陣1 脇本陣1 旅籠32 |
  2009年7月25日 野尻宿からの続き 2009年7月25日 野尻宿からの続き
15:45
■三留野~森林組合
雨が強くなってくる中、道なりに坂を上り、中央本線鉄橋下を潜り、標識を頼りにやってくる。傘で片手が使えず、写真が撮りづらい。
●三留野宿は、明治14年の大火で宿の大半が焼失してしまい主要な建物は焼失したということだった。
歩いていると案内板を発見。●脇本陣であった。
案内板には、「脇本陣は宮川家が務めた。現在の建物は明治の大火以降のものである。・・・とあった。15:58 |
  さらに下り、右側には●鮎沢本陣跡があり、本陣跡は長野地方法務局南木曾出張所になったが、現在は、森林組合の建物が建っている。入口「明治天皇行在所記念碑」が建っている。 さらに下り、右側には●鮎沢本陣跡があり、本陣跡は長野地方法務局南木曾出張所になったが、現在は、森林組合の建物が建っている。入口「明治天皇行在所記念碑」が建っている。
「三留野宿本陣は鮎沢家が代々務めた。ここも明治14年の大火で焼失してしまった。
庭には枝垂梅が町天然記念物として現存しているということだが雨でうっとうしくそれどころではなかった。
本陣の先には●旅籠の雰囲気を残す建物が残っている。 |
  ■森林組合~蛇抜け橋 ■森林組合~蛇抜け橋
本陣を過ぎて左側の●常夜燈を過ぎる頃には、突然雷が鳴り、しばらくするとものすごい豪雨になり、坂道は滝のように雨が流れ、歩けるものでなく、右手にあった集会所の軒先でしばらく避難していた。とても「等覚寺」には行けず、小学校脇から入るという旧道を歩けず、しばらく立ち往生してしまった。しかし4時を過ぎ、妻籠まで行かないといけないし、で雨が収まって来たのをねらって先に進み始めることにした。そんなわけで三留野宿は見るべき所を通りすぎて終わってしまった。坂道を下り、進んで行くと木製の●蛇抜橋を渡る。蛇抜けとは山津波(土石流)のことで、三留野の辺りは土石流に何度も襲われている。 16:25 |
  ■蛇抜け橋~上久保一里塚 ■蛇抜け橋~上久保一里塚
下り坂を道なりに進み、右下方に木曽木材の●貯木場が見えてきた。右奥には「桃介橋」も見えている。桃介橋は大同電力(現関西電力)の読書発電所建設に伴う資材運搬用の橋として架けられた日本最大の木造吊り橋で、廃橋寸前となっていたものを、近代化遺産として整備された。
●JR南木曽駅が貯木場に隣接してある。ここから先中央線は大きく右折して通り過ぎて行き、旧道は妻籠に向かって峠道を歩くようになる。 16:35 |
  ●妻籠宿への坂を上る。雨があいかわらずひどいので、写真がうまく撮れず、ガイドブックも片手で取り出そうにも上手くいかず、道なりに歩いていくしかなかった。歩いていくと右手に、義仲が平家打倒の旗揚げしたとき、義仲の兜の八幡座の観音像を祀ったというかぶと観音があり、さらに進むと、丁字路から●石畳となる坂道をまっすぐ上る。丁字路にある「せん澤」道標には「右妻籠宿へ 下り国道へ 左なぎそ駅へ」とあり、最近建立のものであるけど、うまく周りの風景になじんでいる。 17:00 ●妻籠宿への坂を上る。雨があいかわらずひどいので、写真がうまく撮れず、ガイドブックも片手で取り出そうにも上手くいかず、道なりに歩いていくしかなかった。歩いていくと右手に、義仲が平家打倒の旗揚げしたとき、義仲の兜の八幡座の観音像を祀ったというかぶと観音があり、さらに進むと、丁字路から●石畳となる坂道をまっすぐ上る。丁字路にある「せん澤」道標には「右妻籠宿へ 下り国道へ 左なぎそ駅へ」とあり、最近建立のものであるけど、うまく周りの風景になじんでいる。 17:00 |
  ■上久保一里塚~妻籠宿 ■上久保一里塚~妻籠宿
石畳を上り、しばらく行くと。すぐ先に残っているのは●上久保一里塚で、左右に塚がはっきりと残っている。江戸から「78番目」の塚に当たる。
さらに塚の先の坂道を下りて行くと、左手に、●「良寛の歌碑」と案内板がある。良寛が中山道を通った折りに当地で詠んだもので
・・・「この暮れの もの悲しきにわかくさの 妻呼びたてて 小牡鹿鳴くも」・・・と彫られている。 |
  先はふたたび上り坂となり、しばらく行くと、右手の入る道があり、入口に案内板が立つ。右へ入って行くと●「妻籠城跡」が残っている。妻籠城は「小牧長久手の戦い」で木曽義昌の家臣山村良勝が徳川家康軍を退け、また関が原の戦いで間に合わなかった秀忠は、戦勝の報告をここにいた時受けたという歴史を持っている。 先はふたたび上り坂となり、しばらく行くと、右手の入る道があり、入口に案内板が立つ。右へ入って行くと●「妻籠城跡」が残っている。妻籠城は「小牧長久手の戦い」で木曽義昌の家臣山村良勝が徳川家康軍を退け、また関が原の戦いで間に合わなかった秀忠は、戦勝の報告をここにいた時受けたという歴史を持っている。
次の●妻籠宿の案内板が立つ三つに分かれる所は真ん中のコンクリートに滑り止めの付いた舗装路を行く。かなりの急坂で、滑らないように注意して進んだ
少し行くと妻籠宿の古い建物が見えてきた。本日の泊まりは本陣隣の元旅籠の「阪本屋」さん。30kmを越えよく歩いた。但し今日は野尻で道を間違えたし、三留野は雨で細かく史跡を見ることができなかったのが残念。
宿到着17:35 |
|