
中 山 道
|
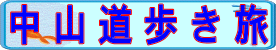 |
16 松井田から坂本宿へ 歩行地 図 |
| 松井田駅-下町交差点-新堀-五料茶屋本陣-下横川-関所跡-坂本宿 10.3 km |
|
16松井田宿
「此の駅を松枝ともいふ」とあり、宿場の規模はそんなに大きくないが、妙義山への追分でもあり、妙義山詣での人々でも賑わっていた。
本陣2 脇本陣2 旅籠14 |
| 2007年11月4日 5時半に越谷を出て、新幹線で高崎まで行き、松井田駅7時55分に到着。下町交差点へ向かう。快晴で気持ちが良い。いよいよ街道の最初の難所碓氷峠を越える。 |
  ■下町~西松井田駅前 ■下町~西松井田駅前
●下町交差点
駅からぐるっと来る道は妙義山道の一つになっていて、交差点の左角の「かんべや」には登山道の古い看板が残っていると調べてあったが、見落としてしまった。少し安中寄りの方には東木戸があったそうだ。又ここの少し左前方に●伝右衛門脇本陣があったといわれる。ここの宿にはいくらか古そうなものは見受けられる。宿の歴史 8:10 |
  ●趣の残る民家 ●趣の残る民家
左手の民家であるが、畑中医院跡といわれる建物でいかにも旅籠風というか雰囲気のある建物。建物の前に榛名道標が立つ。右の方は辻中薬局という店で、蔵造り風な面白い建物。伊勢屋の屋号なので昔は商店かなにかか。県信用組合のあたりが金井本陣跡と言われている。信用組合は全くの普通の銀行で、昔らしさは全然ない。宿内の交通量は少なめ。日曜日のせいでもあるけど。 |
  ●不動寺 8:30 ●不動寺 8:30
宿内の絵看板が架かっていて、山田本陣跡がわかったので、クリーニング屋さんの角を入って行ったが結局わからず、その先に不動寺があった。
●石塔婆と仁王門
門前に石塔婆が3つ並んでいる。自然石に仏種子や文字を刻んだ物。観応3年(1352)と北朝の年号を用いている。仁王門は三間二間の柿葺で桃山時代の様式だが江戸時代の改築だそうだ。ともに県重要文化財に指定されている。本日は晴天で不動寺からの妙義山の眺めが大変すばらしい。 |
   ●松井田八幡宮 ●松井田八幡宮
創立年代は不詳だが、建久八年(1197)に頼朝が立ち寄った記録がある。
江戸時代には家光より朱印地を受けている。本殿は三間二間の流造りで県指定重要文化財で欅作りのかっちりした様式が感じられる。階段左に神社では初めてみるような、六角堂があった。中に神像のような像が立っているけど、解説はない。聖徳太子像と見たがどうだろう。 |
  ■西松井田駅前~五科 ■西松井田駅前~五科
駅前街道に戻ってきて、左手に「商工会館」が洋館風に建っている。また暫らく行くと「西松井田駅前」の交差点がある。右手石垣は松井田城の一部だったそうだ。城は右手奥の山中にあり、最後の城主が北条氏の家臣大道寺政繁で、豊臣秀吉の小田原城攻めで自刃した。 9:00
●補陀寺
大道寺政繁の墓がある。前田家の大名行列が通ると、悔しさに汗をかくという伝説がある。寺らしくなく犬が吠えてうるさい。山門の額に書いてある「関左法窟」とは関東一の大道場という意味だそうだ。鐘楼が印象に残った。 |
  松井田警察署の手前を左に入る道が旧道。やがて左手に一里塚跡がある。というが右側にあった庚申塔を見ながら歩いていたら、通り過ぎちゃった。 松井田警察署の手前を左に入る道が旧道。やがて左手に一里塚跡がある。というが右側にあった庚申塔を見ながら歩いていたら、通り過ぎちゃった。
突き当たりは踏切で、昔はこの踏切を渡るのが
本当の中山道だったらしいのだけど,無くなっているので、踏切を渡らないで線路に沿った道を行き、第十中山道踏切を渡る。ここらの妙義山の眺めも遮る物が無く大変すばらしい。 9:15 |
  ●妙義山 ●妙義山
赤城山、榛名山と共に上毛三山の一つに数えられる。急勾配の斜面と尖った姿が特徴的で日本三大奇形の一つである。
線路を渡った旧道はいかにものどかな田舎道といった感じがある。やがて上信越自動車道の手前で国道を渡るのが旧道で、中山道の標識も出ているけど、信号がない場所なので、車が来ない時にダッシュで渡る。その先の右手の理容店の庭に古い大きな庚申塔と二十三夜塔がある。 |
  ■五科~御料平 ■五科~御料平
●五料の茶屋本陣跡 9:40
理髪店の先を右にはいると、五料の高札場跡があり、線路をまたいで五料の茶屋本陣跡が復元されている。西側が本家で「お西」、東側が分家で「お東」と呼ばれている。両家の先祖は共に天文年中(1532~55)諏訪但馬守が松井田西城を構えたときの家臣中島伊豆直賢と伝えられている。以来五料の名主を務めた家柄。一年交代で茶屋本陣を務めたという。建物は文化三年の焼失後、同年再建された。説明板 |
  道はだらだらと上って行く。JRの榎踏切を渡ると「丸山坂」と呼ばれている。坂の途中青面金剛塔、馬頭観音が数基ある。 道はだらだらと上って行く。JRの榎踏切を渡ると「丸山坂」と呼ばれている。坂の途中青面金剛塔、馬頭観音が数基ある。
●夜泣き地蔵 10:10
頂上の左手にに立つ。・・昔ある馬方が脇に落ちていた地蔵の首を、荷物のバランスをとるために一緒に深谷まで運び、不要になるや捨ててしまった。すると夜な夜な首が泣くので、深谷の人が五料まで戻して胴の上に載せてやったという言い伝えがある。前に置いてある石は「茶釜石」といって、たたくと金属性の音がするというので、置いてある小石で一応たたいてみた。ムム--そんなかなって感じ |
  ■御料平~横川 ■御料平~横川
信越線に遮られるので線路に平行して進む。ただし手前にも踏切があり、ここが線路1本だけ渡ることができるが、2本目の先はガードレールで渡れない。意味がよくわからん。杉の巨木に覆われた●「碓氷神社」がある。碓氷郷の鎮守産土神である。祭神が有名どころ17神もあって驚く。その前にあるJR高墓踏切と国道を渡る。国道を少し戻り、角にJAがある旧道に入る。 10:25 |
  旧道はいったん国道に出て、小山沢交差点でまた脇道へ入っていく。●「百合若大臣の足痕石」というのがある。百合若大臣というのは、伝説上の人物だそうで、なるほど窪みは、足跡のように見えるが、仏足石のようなものを想像するけど、どれがそれだかよくわからなかった。 10:40 旧道はいったん国道に出て、小山沢交差点でまた脇道へ入っていく。●「百合若大臣の足痕石」というのがある。百合若大臣というのは、伝説上の人物だそうで、なるほど窪みは、足跡のように見えるが、仏足石のようなものを想像するけど、どれがそれだかよくわからなかった。 10:40 |
  ■横川~坂本 ■横川~坂本
下横川信号で「第十五中山道踏切」を渡り、●線路の右側を行く。右側のガケから湧水が湧いていて、花壇にきれいに花が咲いている。間もなく「峠の釜めし発祥の地」有名な●「荻野屋」の黄色い看板が見えてくる。横川駅には、碓氷峠を越えるため特急も、鈍行もすべてここで止まり、尻押し用の機関車を増設させた。その時間を利用して「釜飯」を求める客が多かった。 10:55 |
  ●横川駅 11:00 ●横川駅 11:00
現在の横川駅は「長野新幹線」の開通で、すっかり元気がない。おまけに信越線はここで終わっている。昼ごろ到着したが、登山客がちらほらいるだけであった。
●茶屋本陣跡 11:10
右手の武井家に、「群馬県指定史跡横川の茶屋本陣」の標柱が立っている。代々横川村名主を勤め幕末の頃は坂本駅の助郷惣代をも兼ねた武井家である。個人のお住まいのようなので、看板を読むだけで失礼した。 |
  ●横川関所跡 ●横川関所跡
右手に横川関所東門が復元されている。設置の歴史は古く平安時代の昌泰2年(899年)に設けられている。その後の変遷を経て、文禄元年(1592)に設けられ安中藩が管理した。「入り鉄砲に出女」を取り締まった。旅人が手をついてお改めを受けるおじぎ石も残っている。踏切の右、●アプト式線路があったところは遊歩道となって伸びている |
  ●薬師坂 11:30 ●薬師坂 11:30
関所跡を出ると、電車が通ることのないガードをくぐって、国道18号に出る。そのままずっとあるくと突き当たりが薬師坂という。急な坂を上りると再び国道にでてしまうが、ここからゆるい坂を上がっていくと、●高速道が見え、その先の坂本宿に入っていく。 11:40 |
|