
中 山 道
|
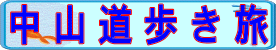 |
42 妻籠宿から馬籠宿へ 歩行地図 |
| 妻籠宿-本陣跡-寺下-大妻籠-一石栃立場-馬籠峠-峠集落-馬籠宿 7.6 km |
|
42 妻籠宿
妻籠宿は中山道と飯田街道の分岐点に位置し、古くから交通の要所として栄えた。明治以後、国道、鉄道が通らなくなったこともあり妻籠宿は発展から取り残され、衰退の一途をたどることとなった。しかし逆に江戸時代の宿場の姿を色濃く残している町並みが見直され、町並み保存運動が起こり、国の重要伝統建造物保存地区第1号に選定される。町並みは、江戸時代にタイムスリップした感じで、どれも当時の面影を残た情緒いっぱいの宿場町が続いている。 江戸方から下・中・上の3町があり、桝形をはさんで寺下の町並が続いていた
本陣 1 脇本陣跡 1 旅籠 31 |
   2009年7月26日旅籠阪本屋さんを8時前出発 2009年7月26日旅籠阪本屋さんを8時前出発
■妻籠宿~本陣跡
妻籠宿入口すぐ左手に「鯉岩」があるが、明治時代の地震で頭が落ちたそうで、鯉の形を想像するのはいささか難しい。 左手の●口留番所跡から妻籠宿が始る。この場所で通行する人を見張っていた訳である。 平日で朝も早く、人通りは地元の人が犬を散歩させていることぐらいしか見かけられない。 その先右手には●高札場が復元されている。高札場跡左手には小さな●「水車小屋」も設けられている。 |
  ●歴史的建造物保存地区 ●歴史的建造物保存地区
奈良井と共に「歴史的建造物保存地区」に指定されている。特に妻籠宿は、町並み保存に力を入れ、1976年その第1号に指定された。宿入口からすでに江戸時代を思わせる●民家がずらりと並んでいる。
町並の復元にも力を入れていて、電柱なども見えないように工夫されている。整然と並ぶ家並みは見事で、宿泊した「阪本屋」の主人の話では保存を第一に、改修の時も自費で行い、景観を壊すことは許されないという。住宅として使用しているので中々維持が難しいと思う。 |
  ■本陣跡~枡形跡 ■本陣跡~枡形跡
右手●脇本陣奥谷(林家住宅)は木曽五木の禁制が解かれて明治10年に総檜造りで建て替えられたもので、国の重要文化財に指定されている。島崎藤村の初恋の相手「ゆふ」さんの嫁ぎ先でもあります。
道の向こう側には●本陣跡がある。島崎氏が任命され、明治に至るまで本陣、庄屋を兼ね勤めました。島崎藤村の母の実家でもあった。兄の島崎広助が東京に出たため明治20年代に建物は取り壊された。 現在の建物は復元された建築のもの。残念ながら両方とも昨日は遅く着いて、今日は朝早くて、閉館中で見る機会がなかった。 |
   ■枡形跡~寺下 ■枡形跡~寺下
本陣の隣は昨日宿泊した元旅籠の●「阪本屋」さん ここも築150年とか。食事が沢山で食べられないくらい。一人でも泊めてくれた。
右手にある●郵便局は宿場の雰囲気を壊さないように旅籠風な造りになっている。 左手に石仏「寒山拾得」像がある。1984年の長野県西部地震で石垣が崩れ、その中から発見されたものだが、この像は他に類例がない珍しいものだそうだ。●枡形を右手に下りていく。枡形には石垣が残り、常夜燈も建っている。8:15 |
  ■寺下~大妻籠 ■寺下~大妻籠
枡形を下りていくと右手に旅籠で今も民宿の●下嵯峨屋、松代屋が並んで建っている。下嵯峨屋の方は資料館が併設されていて、そちらは屋根に石が乗り、妻籠宿における庶民の住居を代表する片土間に並列2間取の形式をよくとどめているとか。
この先風情ある●寺下の町並みが続く。最初に保存事業が行われた寺下地区は、妻籠宿の原点とも言うべき町並みですと・・・しかしここは復元された建物が多いのではないかと思う。
その先の上嵯峨屋は、18世紀中期の木賃宿の様式をよく留め町有形文化財になっている。このあたりで妻籠宿も終りになります。 |
  宿を過ぎて、飯田道が分岐する尾又追分だったところに「土地の精霊神」やら「酒神」とか諸説がある「「おしゃごじさま」がを祀られている。 宿を過ぎて、飯田道が分岐する尾又追分だったところに「土地の精霊神」やら「酒神」とか諸説がある「「おしゃごじさま」がを祀られている。
妻籠発電所を過ぎて、左手にお土産屋の●「いんきょ」という店があり、なんと珍しい藁馬の実演販売をやっている。 8:35
国道256号を横断して、広い駐車場の脇に入っていく。●入口に「中山道碑」がっている。馬籠までは6.9kmの地点。
大妻橋手前に「飯田街道追分の石柱道標の案内板」が立っている。が、しかし、道標らしきものはまわりを見回してもなんにもなく、地震か何かで倒れたまんま放置しているのかと思ったがよくわからず。 |
   ■大妻籠 ■大妻籠
県道から右折して、石畳道に入り、ここからいかにも旧道という風情の●山道を進み、しばらく行くと●大妻籠の入口に入る。
●大妻籠集落は妻籠宿の「奥座敷」といわれ、立場として賑わった。 現在も古い建物や民宿が多く、「うだつ」の上がる家もある。 |
  集落の途中、案内標識に従って、暑い中右手へ上っていくと、●県宝藤原家住宅がある。間取り・構造・仕上りから17世紀半ばの建物と推定されている。休むだけの茶屋(馬宿)を営み、間口5.5間ほど。ただしここは農家の奥にあって、入りづらい所にあるが一般公開されている。 集落の途中、案内標識に従って、暑い中右手へ上っていくと、●県宝藤原家住宅がある。間取り・構造・仕上りから17世紀半ばの建物と推定されている。休むだけの茶屋(馬宿)を営み、間口5.5間ほど。ただしここは農家の奥にあって、入りづらい所にあるが一般公開されている。
旧道に戻り、再び国道に合流する所に●大妻籠一里塚跡がある。塚の跡は無くなっていて、跡地に「中山道庚申塚の石碑」や馬頭観音像などが建つ。9:10 |
  ■大妻籠~男滝・女滝 ■大妻籠~男滝・女滝
県道の向こうに見える●石畳道が旧道で、案内標識に従い、山道を登って行く。見事な石畳が復元されているが少々歩きづらい。
しばらく行くと左手に●倉科祖霊社という祠が建っている。松本城主小笠原貞慶の重臣倉科七郎左衛門の霊が祀られている。伝説では京都に宝競べに行く途中盗賊に殺されたというが、史実では大阪への帰り道、土豪の襲撃に遭い、従者30余名と討ち死にしたという。 9:25 |
  先の坂を上がったところで、道は2つに分かれ、旧道は左手の細い山道に入るが、男滝・女滝を見るため右手の坂を下ることにした。右手の道は急な下り坂で、下りた先に●「男滝」奥に●「女滝」が見られる ここの滝は吉川英治が「宮本武蔵」の舞台として登場させたことで知られているということだけど、読んだことがない。それにしても道中の途中、誰にも出会わないので、滝の音を聞いているといささか怖い覚じだ。 滝から階段を上って滝見茶屋の脇から県道7号線に出る。茶屋は営業していなかった。 9:30 先の坂を上がったところで、道は2つに分かれ、旧道は左手の細い山道に入るが、男滝・女滝を見るため右手の坂を下ることにした。右手の道は急な下り坂で、下りた先に●「男滝」奥に●「女滝」が見られる ここの滝は吉川英治が「宮本武蔵」の舞台として登場させたことで知られているということだけど、読んだことがない。それにしても道中の途中、誰にも出会わないので、滝の音を聞いているといささか怖い覚じだ。 滝から階段を上って滝見茶屋の脇から県道7号線に出る。茶屋は営業していなかった。 9:30 |
  ■男滝・女滝~馬籠峠 ■男滝・女滝~馬籠峠
国道を少し下りて行くと、右に馬籠宿への案内標識があり、小さい橋を渡り●右手の石畳のある山道に入って行く。また石畳道を行くと、一石栃白木改番所跡がある。木曽五木をはじめとする伐採禁止木の出荷統制が行われた。すぐ上に「立場茶屋」がある。
●「立場茶屋」(牧野家住宅)
一石栃は妻籠と馬籠の中間にあたり、往時は7軒ほど茶屋があったが、現在ではこの「牧野家住宅」だけが残る。ボランティアの人がいて、お茶などで接待してくれる。外人やら結構人がいたけど、馬籠からやってきた人らしい。 9:55 |
  ■馬籠峠~馬籠宿 ■馬籠峠~馬籠宿
茶屋を過ぎると、かなりの急坂が続き、橋を渡ったり、石畳道を上ったりで汗かいて、いささかげんなりして行くとようやく馬籠峠頂上に出た。
ここには●茶屋もあり、自動販売機もあった。しかし空缶の始末ができないので、飲んだら持って行けというので、空缶はリュックにしまっておいた。 馬籠峠は標高801mの峠であり、県道が通っている。正岡子規の句碑があが、写真を撮り忘れてしまった。県道を少し下りて、●右方向へ進むのが旧道 |
  旧道へ入ると左手に「熊野神社」があり、●峠の集落へ入って行く。江戸時代の建物もあって、幕末の頃、ここの牛方が中津川の問屋に対抗して荷物の付け出しを拒否するというストライキを行い、勝利したという歴史がある。 旧道へ入ると左手に「熊野神社」があり、●峠の集落へ入って行く。江戸時代の建物もあって、幕末の頃、ここの牛方が中津川の問屋に対抗して荷物の付け出しを拒否するというストライキを行い、勝利したという歴史がある。
坂を下り続ると、右側に「あずま屋」が建ち、休憩所となっている。●十返舎一九歌碑もあり、ほとんど読めないが、 ・・・渋皮のむけし女は見えねども 栗のこはめしここの名物・・・。とほってあるそうだ
この地には古くから栗こわめしを名物にしていた茶屋があった。 10:25 |
  県道を2度横断し、石畳の●「梨の木坂」を下って行く。下り切って又県道を横断し、「中山道」碑の立つ石畳道を下る。ここら辺の石畳はきれいなので、復元されたものと思う。 県道を2度横断し、石畳の●「梨の木坂」を下って行く。下り切って又県道を横断し、「中山道」碑の立つ石畳道を下る。ここら辺の石畳はきれいなので、復元されたものと思う。
林の中やなにやらいろいろと進むと、県道の右側から●階段を上る旧道に入り、坂道を上がる。この坂道は「陣場坂」と呼ばれていた。ここを上がると馬籠宿に到着する。 10:45 |
|