
中 山 道
|
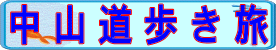 |
52 鵜沼宿から加納宿へ 歩行地図 |
| 鵜沼東町-羽場町-各務原-三柿野-六軒-那加-新加納-切通-長森-加納本町 16.5 km |
|
52 鵜沼宿
 沼宿は古代から、交通・経済の要衝として栄えた土地で、東山道の駅があったところである。室町時代には応仁の乱をさけた、五山派の文人達が移り住んだともいわれる。 宿場としては長さ7町半(約820m)、大安寺川を境に東町と西町に分れていた。次の加納宿まで中山道で2番目に長く、荒涼たる各務原を越え、新加納を経て4里7町(約17km)もあった。宿場は明治24年の濃尾大地震でほとんど倒壊してしまって、昔の面影はほとんど残っていない。 沼宿は古代から、交通・経済の要衝として栄えた土地で、東山道の駅があったところである。室町時代には応仁の乱をさけた、五山派の文人達が移り住んだともいわれる。 宿場としては長さ7町半(約820m)、大安寺川を境に東町と西町に分れていた。次の加納宿まで中山道で2番目に長く、荒涼たる各務原を越え、新加納を経て4里7町(約17km)もあった。宿場は明治24年の濃尾大地震でほとんど倒壊してしまって、昔の面影はほとんど残っていない。
本陣1 脇本陣1 旅籠25 |
  2009年8月25日 太田宿からの続き 2009年8月25日 太田宿からの続き
■鵜沼東町~国道21号バイパス
「うとう峠」から下りてくると五差路の左側の角に、●「鵜沼宿」の道標がある。「ここは中山道鵜沼宿 これより うとう峠 左」 と彫られている。これはライオンズクラブによる最近のもの。
この●五差路の先が 宿の始りといわれ、右側には●常夜燈が立っている。9:30 |
   常夜燈から少し行くとバイパスが北から来ており、右側にかって赤坂神社前にあった●高札場が復元されている。 常夜燈から少し行くとバイパスが北から来ており、右側にかって赤坂神社前にあった●高札場が復元されている。
また村境を示す●傍示石が国道を挟んで、東西に復元されて立っている。実際の立っていた位置はこんなに近いわけではなく、西へ2、3kmほど行った各務原で、傍示石間の距離も1km位ある。
各務原は天領や尾張藩領、旗本領などに分かれて治められていて、各藩はあちこちに傍示石を立てている。この道標には、それぞれ「是より東尾州領」、「是より西尾州領」と刻まれ、明冶以降街道沿いから撤去され、その後鵜沼中学校内に移設されていたが、坂祝バイパス完成にともないこの地に移設された。 |
  ■国道21号~鵜沼西町 ■国道21号~鵜沼西町
バイパス交叉点の左手に●問屋・野口家跡があります。鵜沼宿の問屋・東町庄屋を兼務していました。 現在は昔風の建物が建ち、喫茶店になっている。 。少し先に安寺川へ架かる●大安寺大橋(昔は八間橋という)がある。橋を挟んで東町と西町と呼ばれていた。常夜燈の脇に道標が立っていて、「太田町へ二里八丁」とあるので明治のものかもと思う。 橋を越えると、鵜沼宿の中心部になります。9:50 |
  橋を渡った右手に●町屋館があります。ここは江戸時代には「絹屋」という屋号で旅籠を営み、明冶の初めから昭和30年代まで郵便局を営んでいた、旧武藤家の住宅です。現在は各務原市の資料館となっている。主屋は明冶24年の濃尾震災で倒壊し、その後、再築されたもので、江戸時代の旅籠の形式を残しています。ここで鵜沼宿の資料を各種もらえた。 橋を渡った右手に●町屋館があります。ここは江戸時代には「絹屋」という屋号で旅籠を営み、明冶の初めから昭和30年代まで郵便局を営んでいた、旧武藤家の住宅です。現在は各務原市の資料館となっている。主屋は明冶24年の濃尾震災で倒壊し、その後、再築されたもので、江戸時代の旅籠の形式を残しています。ここで鵜沼宿の資料を各種もらえた。
●鵜沼宿の町並
鵜沼宿は、濃飛大地震により壊滅的な打撃を受けてしまったが 唯一残った茗荷屋梅田家住宅が江戸の旅籠の姿を残し、町並も静かな雰囲気が感じられた。 |
  町屋館の向い側には●菊川酒造があります。 町屋館の向い側には●菊川酒造があります。
明治4年の創業で倉庫群は登録有形文化財となっており、鵜沼宿のシンボルとなっていますということでした。 右手の工事中の場所は「問屋・脇本陣の野口家跡」。野口家は敦賀城主大谷刑部吉隆の三男・大谷久右衛門吉矩の子孫と伝えられ、関ヶ原の戦いに敗れたあと、許されて野口と姓を改め、鵜沼宿で問屋を務めることになったという。脇本陣再建工事中で、フェンスに●完成図が貼ってあった。 |
   ■鵜沼西町~鵜沼羽場町 ■鵜沼西町~鵜沼羽場町
先に進み、●旧家らしき家など眺めながら行くと、宿の西出口にあたる●交差点へ出る。鵜沼宿西口の道標が左側にあったらしいが見逃してしまった。 交差点を越えしばらく行くと、右手に●衣裳塚古墳というのがある。 岐阜県下最大の円墳ということであるが、前方後円墳の可能 性もあるらしい。 10:10 |
   旧道を西へどんどん進んで行く。左手南方遠くに●犬山城が見えている。ここから2キロ位の所にある。 旧道を西へどんどん進んで行く。左手南方遠くに●犬山城が見えている。ここから2キロ位の所にある。
衣装塚古墳から700m位の右手に●津島神社がある。案内柱に村芝居を上演した「皆楽座」があり回り舞台になっており文化財ですとあるのだけど、公開されておらず、どのようなものかわからなかった。ここも濃尾震災により倒壊したが、明冶32年に再建されたという。●津島神社藩塀というものが皆楽座の南側に隣接して立っている。 10:25 |
  ■鵜沼羽場町~三柿野 ■鵜沼羽場町~三柿野
津島神社から5分も歩くと、●国道21号に合流してしまう。ここから先は国道を歩くことになるが、大して見るべき所もないので時間を稼ぐため、早足で進むことにした。
「山の前町」信号を通過すると、国道がJP高山本線と立体交差している所がある。そこを越さずに側道を行くと、左手に●播隆上人碑があります。槍ヶ岳開祖の播隆上人の碑だけど、濃飛地震で真っ二つに折れたままだそうで、すごい形をしている。ここは各務原の一里塚跡でもあり、脇に「旅人道中安全」の石碑も立っていた。 10:50 |
  ■三柿野~六軒 ■三柿野~六軒
名鉄「二十軒駅のあたりは昔立場があって賑わっていたという。やがて「川崎重工」工場が見えた所で左手の側道に入り、名鉄「三柿野駅」前を通ることになる。このあたりの南側はすでに、「航空自衛隊岐阜基地」が広がっており、国道からは滑走路は見えないが、●管制塔だけが見えた。時折爆音と共にF-4あたりが離陸しているのが見えて、写真の一枚も撮りたいと思ったが、どうにもタイミングが合わず撮れなかったのが残念。
●「蘇原三柿野町」交差点から右手の旧道へ入って行くことになる。 11:50 |
   旧道に入った所が●「六軒」といって、昔は「六軒茶屋」と呼ばれていた立場で、茶屋が六軒並んでいたからこの名が残っている。右手に●一里塚跡を示す標柱が立っていて、「六軒一里塚」と呼ばれる。 旧道に入った所が●「六軒」といって、昔は「六軒茶屋」と呼ばれていた立場で、茶屋が六軒並んでいたからこの名が残っている。右手に●一里塚跡を示す標柱が立っていて、「六軒一里塚」と呼ばれる。
右手に●神明神社がある。ここで祀られている馬頭観音は三面六臂で穏やかな美しい姿で印象に残った。 |
   ■六軒~新加納 ■六軒~新加納
このまま旧道を行くと、現在の●各務原市の中心部に入るわけで、この通りには市役所や消防署、警察署なども並んでいる。その手前になんと●「信長町」というバス停があり、地図を見ると那加信長町であり、その先が那加織田町であった。合わせると「織田信長」だね。
「新加納町交差点」で右手に入ると、右手に●日吉神社がある。本殿は奥まった所にあり、赤い派手な鳥居が立っている。本宮は有名な大津市の日吉神社であり、境内には樹齢数百年の檜、杉の大木が林立していたが、伊勢湾台風で倒木してしまったという。 13:00 |
  ■新加納~切通 ■新加納~切通
●間の宿・新加納立場
日吉神社のすぐ先で二股にぶつかり、ここが間の宿だった、新加納立場の入口になる。二股の所が一里塚でもあった。新加納立場の案内板が立っている。鵜沼から加納までは4里10丁もあり、中山道では2番目に長い距離なので、どうしても中間に休憩場所を設ける必要があり、この立場が間の宿として発展した。真っ直ぐ来て右折しないで、左折すると、旗本「坪内氏」の●御典医だった家の黒塀が続く。(この家は現在も医院をやっているらしく看板が出ている)。 13:20 |
  黒塀の先を右折した先に●少林寺がある。少林寺はこの地に陣屋を置いていた、旗本「坪内氏」の菩提寺で、近くに陣屋もあったらしい。 黒塀の先を右折した先に●少林寺がある。少林寺はこの地に陣屋を置いていた、旗本「坪内氏」の菩提寺で、近くに陣屋もあったらしい。
また元の右折地点へ戻って旧道に合流する。左折して旧道を行くが、その先は普通の道で松並木があったというけど今はなにもない。
東海北陸自動車道をくぐり、高田、蔵前と通過していくと、「切通」という所に出る。左手に●「手力雄神社」入口を示す鳥居が見えてきて、本殿へ行こうと思ったが700m位先にあるのでやめといた。この神社は織田信長の崇敬も厚かったといわれた神社であった。 |
   ■切通~領下 ■切通~領下
この先は●切通という。鳥居の先、右手の岐阜信用金庫前には「切通の由来」についての案内板が設けられており、古来東西交通の要路にあたり、このあたり立場が設けられ、茶屋・菓子屋などが設けられ賑いを見せたという。「長森細畑」交差点を過ぎて、右手に●変った看板が目に付いた。文字が薄くてわかりづらいが虎か犬のマークと「明治水」とある。これはネットで調べてもわからずじまい。この先に●細畑一里塚が両塚残っている。14:25 |
  ■領下~加納八幡町 ■領下~加納八幡町
旧道は●二股に出る。角に地蔵堂と道標が立っている。「左は伊勢・名古屋近道」とあって、ここは右へ行くのが中山道である。
先は●「領下」と呼ばれていた集落で、左手には古い「八幡宮」も残っている。
さらにしばらく歩き、JR東海道線高架下をくぐってから、名鉄名古屋線の「茶所」駅の踏切を越えます。
14:35 |
  ■加納八幡町~加納新町 ■加納八幡町~加納新町
踏切を越えたすぐ先、左手に●道標と「鏡岩の碑」というのがが見られる。鏡岩とは江戸時代の相撲取り「鏡岩浜之助」にちなむもので、二代目鏡岩も跡をついでいたが、素行が悪いのに改心して、父の十三回忌にここに碑を建立し、供養をしたのがこの碑だという。
中山道はこの先枡形跡を右に左と曲っていくようにになる。加納城大手門まで六ヵ所の枡形があったと いう。まず第一の枡形を右折して、「新荒田川」に架かる●加納大橋を渡って、●明治時代の道標で左折する。先は広い道路を横切り左折して行った突き当りが「善徳寺」で、「今井本」では東の番所であると書いてあったので、寺までつーと通過してしまったが、その手前に「東番所跡」碑が立っていたらしく、その碑は見逃したようだ。この先「岐阜駅」まで写真を撮りながら、街道を歩いて行った。次回は「善徳寺」から始めたいと思う。本日はこれまでで、16時頃の電車で、「岐阜」から名古屋へ出て、新幹線で東京へ帰りました。 15:20 いう。まず第一の枡形を右折して、「新荒田川」に架かる●加納大橋を渡って、●明治時代の道標で左折する。先は広い道路を横切り左折して行った突き当りが「善徳寺」で、「今井本」では東の番所であると書いてあったので、寺までつーと通過してしまったが、その手前に「東番所跡」碑が立っていたらしく、その碑は見逃したようだ。この先「岐阜駅」まで写真を撮りながら、街道を歩いて行った。次回は「善徳寺」から始めたいと思う。本日はこれまでで、16時頃の電車で、「岐阜」から名古屋へ出て、新幹線で東京へ帰りました。 15:20 |
|