
中 山 道
|
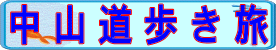 |
54 河渡から美江寺宿へ 歩行地図 |
| 河渡-生津-糸貫橋-本田松原-五六橋-美江寺 4.1 km |
|
54 河渡宿
河渡宿は長良川の渡しの為にできた宿であり、長良川の川幅は常水で50間(約90m)洪水の時は150間(270m)のもなった。川止の時はかなり混雑したという。町の長さは3町(327m)、東町、仲町、西町と続いていた。地理的には長良川の土手近くにあり、低湿地帯にあり、絶えず水害が絶えなかった。文化10年(1813)地盤の土盛りがされ、宿の高さが周囲より5尺ほど高くなった。
本陣1 脇本陣0 旅籠24 |
  2009年10月24日、加納宿よりの続き。 2009年10月24日、加納宿よりの続き。
■河渡~慶応橋
長良川の土手から階段を下りると●「いこまい中山道河渡宿」の幟が見え、宿に入って来た雰囲気を感じる。
土手の下手に建つのが●愛染堂という。
河渡宿の荷駄人足が天保13年(1842)に100文づつを出し合い、愛染明王を祀るため建立したもの。元々宿入口の左側にあったものが老朽化したため、この所に移転し建て直された |
  ●河渡宿の町並 ●河渡宿の町並
昭和20年空襲により、宿場は全焼して古い町は跡形も無くなっている。また長良川の改修により東側がなくなってしまった。しかしあちこち「河渡宿」の木造の常夜燈が立つなど、宿の保存には力を入れている。
 ●河渡宿一里塚跡 ●河渡宿一里塚跡
「河渡宿」碑と「一里塚」碑とが一緒に立ててあり、また文化10年に土盛をした際の代官「松下内匠」を祀った●「松下神社」を建てたという碑が半分無くなって立っている。 11:06 |
  宿の途中の電柱に●「いこまい祭」のポスターが貼ってあって、眺めていたら、車からおじさんに声をかけられ。「明日に祭がありますよ・・・」と言われたけど、「明日はここにいないです-」と答えたら「それは残念なり-」と笑われた。「いこまい」とは、行きましょうの意味らしい。時代行列が行われるとポスターに出ていた。 宿の途中の電柱に●「いこまい祭」のポスターが貼ってあって、眺めていたら、車からおじさんに声をかけられ。「明日に祭がありますよ・・・」と言われたけど、「明日はここにいないです-」と答えたら「それは残念なり-」と笑われた。「いこまい」とは、行きましょうの意味らしい。時代行列が行われるとポスターに出ていた。
●「河渡宿」の道標を見つつ、河渡宿を抜ける。しかしこんな所も空襲にあったとは驚きで、岐阜の巻添えにあったのだろう。 11:15 |
  ■慶応橋~生津 ■慶応橋~生津
しばらく進むみ●慶応橋を渡り、生津の交差点でコンビニを見つけお昼を確保。このあたりも食堂などが見あたらず、今日もおにぎりですますことになった。
道は右寄りに向い、正面に●木が一本張出して、祠がある場所に出た。植木から「神」の一文字だけが見える石碑が立っており、近寄って見ると「「神仏敬信、忠君愛国」などと彫られている。これは道標を兼ねている。 11:45 |
  ■生津~本田松原 ■生津~本田松原
「糸貫橋」を渡ると「本田」で、左手に●「本田の延命地蔵」がある。案内ではこの地蔵は、90cmの石の座像像で彫りが美しく優雅な面相で、背面に「石工名古屋門前町大坂屋茂兵衛」、
台座には「文化六巳巳歳(1809)八月二十四日建立 濃州本巣郡上本田村」と刻まれています。とある。
●代官所跡の説明板を読むと、このあたり幕府の直轄地で、このあたりに陣屋があった。 11:56 |
  ■本田松原~美江寺東口 ■本田松原~美江寺東口
代官所跡のすぐ左手に●高札場跡がある。「中山道分間延絵図によるとこの辺りにあった」とあります。
●「本田松原」の交差点右手に一本の大木が往時を偲ばせるかのように立っている。
12:01 |
  五六川に架かる●五六橋を渡ると両側は田園地帯である。五六橋とは面白い名前だけど美江寺宿は五十六番目の宿であることに由来するらしい。(日本橋を数えて) 五六川に架かる●五六橋を渡ると両側は田園地帯である。五六橋とは面白い名前だけど美江寺宿は五十六番目の宿であることに由来するらしい。(日本橋を数えて)
歩いている時は気づかなかったが、左手には「さぼてん村」というのがあってこのあたりはサボテン栽培で有名であるといいうことだった。
●樽見鉄道の踏切を渡る。踏切を越えたあたりが美江寺宿入口だったという。 12:15 |
|