
中 山 道
|
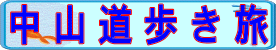 |
6 桶川から鴻巣へ 歩行地図 |
| 桶川-市役所入り口-北原-二ツ家-本宿-東間-鴻巣 8.3 km |
|
6 桶川宿
桶川宿は、江戸から出た旅人が最初に宿泊することが多い場所となっている。現在の町並みは、寛永12年(1635)にほぼ完成し、周辺地が口紅や食紅の原料となるベニバナの生産地として、出羽の最上に次ぐ全国2番目の生産量を誇るようになり、その問屋が店を並べるようになったため繁盛した.荒川の太郎右衛門河岸から江戸へと出荷され売りさばかれたが、明治以降化学染料の普及でべにばなは衰退に向かう。旧中山道と国道17号が分岐したため、道幅改修などのあおりを受けず、さらに戦災も免れたため、建築物も残り、宿場の面影を有している。
本陣1、脇本陣2、旅籠36 |
 ■桶川から市役所入口 ■桶川から市役所入口
●南の木戸
宿は東1丁目と2丁目の境目から始まる。そこに「南の木戸」の石碑が建っており、江戸側の入り口である。朝夕には木戸番によって開け閉じされ、日中も木戸番が見張をしていた。桶川市は宿場の保存に熱心なようで、案内所も整備してあるし古い商屋などもちらちら残り、好ましい。 |
   ●旧家・竹村旅館 ●旧家・竹村旅館
街道に戻りと駅への道の角に竹村旅館がある。江戸末期には、三十六軒もの旅籠があったそうだが現在残っているのは、ここだけ。現在も営業中。このあたりはこのような旧家、土蔵造りの家が多い。この宿には宿場館という案内所があって資料を仕入れるのに便利。中山道の埼玉県分の地図をもらえた。 |
   ●本陣 ●本陣
府川本陣、門の奥に明治天皇行在所の碑が立っている。中には入れない。
●大雲寺・女郎買地蔵
弘治5年(1557)に建立された大雲寺には、宿場関係者の墓石が多い。本堂の傍らに、人間に化けて宿場の飯盛女と遊んでいたため動かないように背中にかすがいをうちつけられたという女郎買い地蔵がある。 |
   ●稲荷神社 ●稲荷神社
街道右手少し奥まった所にある。拝殿の両側に「紅花商人中」と刻まれた石灯籠が2基並んでいる。桶川は紅花の産地でもあり、取引も盛んであった。右側に力石が置いてある。610kgもあるもので日本一と言われる。嘉永5年2月岩槻の三ノ宮卯之助という者が初めて持ち上げたと案内にある。 |
  ■市役所から北本 ■市役所から北本
●北の木戸
西1丁目と西2丁目で宿は終わるが、それを示す碑。碑の前はそば屋さんで食べていきたかったがお昼時で混んでいて断念。
●桶川宿のモニュメント
宿はずれを示す「中山道桶川宿碑」傍らの緑色のものはイスで休憩できるスペースもある。 |
   ●ケヤキ森 ●ケヤキ森
桶川を出て、北本へ向かう。武蔵野特有のケヤキの森があちこと残っていてうれしい。ケヤキは夏は茂って日を遮り、冬は葉が落ち腐葉土になるもので埼玉県の木にもなっている。一番右の写真は北本市東間あたり。 |
   ■北本から鴻巣 ■北本から鴻巣
●北本宿の碑
北本は元々の中山道の宿場で慶長のころ(1615)に鴻巣へ宿が移され。そのため北の元宿ということから北本の地名となっている、
案内板
●多聞寺のムクロジ
北本駅の手前に多聞寺がある。樹齢推定200年といわれるムクロジの巨木があり、県の天然記念物。うしろに天神社もある。ちょとした市が立っていた。 |
  中山道はまっすぐ進むが、慶長のころの初期中山道は北本駅を斜め左へ入り、踏切を越して、線路に沿って行き、再び旧道に合流していく。踏切のそばに一里塚がある 中山道はまっすぐ進むが、慶長のころの初期中山道は北本駅を斜め左へ入り、踏切を越して、線路に沿って行き、再び旧道に合流していく。踏切のそばに一里塚がある
●馬室原一里塚
今は西側の塚だけが残り、東側は高崎線によりなくなった。
線路の東側に浅間神社がある。
●浅間神社
かなり大きい境内を持つ神社である。富士塚の上に本殿があるはずだけど、不審火により全焼したそうで頂上には何もなく、小さな拝殿が階段の途中に置かれている。この先鴻巣へ入るが、手前は人形町という。鴻巣は人形の町でもある。本日はこれで終わり鴻巣駅から帰宅する。 17.7km |
|