
東 海 道
|
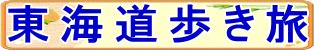 |
25 日坂宿から掛川宿へ 歩行地図 |
| 日坂-八幡宮前-伊達方-千羽-馬喰橋-新町 6.9km |
|
25日坂宿
日坂宿は、西に掛川宿、東に金谷宿という大きな宿場にはさまれ、東海道の宿場としては坂下(現三重県鈴鹿)、由比に次いで三番目に小さな宿場であった。東の本町から下町、古宮町とゆるやかなカーブを描いている。鉄道が通っておらず静かな町並みはよく保全されている。
本陣1 脇本陣1 旅籠屋33 |
  2007年12月1日の続き 12:25 2007年12月1日の続き 12:25
■日坂~古宮
まず宿にはいると大きな●秋葉常夜燈が迎えてくれる。安政三年(1856)の建立のものが朽ちたので平成10年に復元したもの。 11:25
●町並み
大井川の川止めなどもあり、小さな宿場ではったけど、かなりの賑わいであっただろうと思う。宿場の東口から西口までの距離は、およそ六町半(700メートル)町並みの形態は現在もあまり変わっていないといわれる。国道1号が通るものの、鉄道がなく、落ち着いているのか、寂れているというべきか微妙。昼時になったが、食堂などはなかったので、本日も車の街頭販売のパンなどでしのぐことになった。 |
  ●本陣跡 ●本陣跡
日坂宿本陣は代々片岡家が世襲で営み、嘉永五年(1852)の日坂宿の大火で全焼、再建後、明治三年(1870)に店を閉じました。
その後の跡地を日坂小学校の敷地としている。
●脇本陣「黒田屋跡
脇本陣「黒田屋の跡で面影はまったく残っていない。明治天皇の行幸のさい小休止場所として利用された。 |
  ●藤 文 12:30 ●藤 文 12:30
日坂最後の問屋役を務めた伊藤文七邸。明治四年には、日坂宿他二十七ヶ村の副戸長に任ぜられました。その間、幕府の長州征討に五十両を献金、明治維新の時は官軍の進発費として二百両を寄付しております。明治四年の郵便制度開始と同時に郵便取扱所を自宅・藤文に開設、取扱役(局長)に任ぜられました。日本最初の郵便局の一つと云われています
●萬屋
江戸時代末期の旅籠。嘉永五年(1852)の日坂宿大火で焼失し、その後まもなく再建されました。同じ宿内で、筋向かいの「川坂屋」が士分格の宿泊した大旅籠であったのに対して「萬屋」は庶民の利用した旅籠でした。・・・・・いずれも案内板より |
  ●旅籠・川坂屋 ●旅籠・川坂屋
宿で一番西にあった旅籠屋で上段の間をもち身分の高い武士などが宿泊したようで、脇本陣格であったと思われます。江戸時代の面影を遺す数少ない建物の一つで精巧な木組みと細かな格子が特徴的。復元工事がされて一般公開している
●高札場(復元)
ここに掲げられている八枚は「東海道宿村大概帳」の記録に基づき天保年間のものを復原したもの |
  ■古宮~事任八幡宮 ■古宮~事任八幡宮
●下木戸跡
宿場の木戸は大規模な宿場では観音開きの大きな門でしたが、小規模であった日坂宿では木戸の代りに川がその役割を果たしていた。
●下木戸の秋葉常夜燈
日坂宿には入り口にあった、安政3年のものとこの弘化2年(1845)のもの、及び相伝寺境内にあるものと3基残っている。 |
  ●事任八幡宮(ことのまま) 12:50 ●事任八幡宮(ことのまま) 12:50
宿を出て、朱に塗られた歩道橋で国道一号線を渡り、事任八幡宮の境内に入る。境内は巨木が鬱蒼と繁り、神域の雰囲気がよく出ている。延喜式に記載があるほど、昔から街道筋にあった古いお宮で、『枕草子』にも名前が見られる。康平五年(1062)源頼義が石清水八幡宮を当社に勧請し、以来八幡宮を併称す。 |
  ■事任八幡宮~成滝 ■事任八幡宮~成滝
国道一号線バイパスの八坂インターにかかり、バイパスを潜ると、道は国道一号線から伊達方の集落へ、左へ別れる。
●旧東海道「伊達方一里塚」
公園風のとてもきれいな一里塚跡で、日本橋から数えて五七番目のもの。
この先二キロほど国道を歩き続けるとやがて「成滝信号」に出るが、旧道はこの成滝信号から国道と分かれて左手に入っていく |
   ■成滝~七曲 ■成滝~七曲
左手の旧道に入り、途中に●かわいい道祖神などが立っている。
やがて「●馬喰橋」の交差点に至る。 馬喰橋と言えばあの弥治さん喜多さんが座頭をからかって川に突き落とされた場所で有名だそうな。橋詰には一里塚跡がある。五八番目の物で、●当時は「葛川の一里塚」と呼ばれていた |
 ●掛川宿入口七曲 14:15 ●掛川宿入口七曲 14:15
掛川宿場入口は現在のバス停「新町」付近からで、左手に曲がる。「東海道七曲」の標識があるといわれているが、見あたらなかったが。特に案内など見あたらなかったし、事前に学習しておかないと、ここが七曲の始めだとは気がつかない。バス停を直進していっても、掛川の町に入るが、やはりここはこだわっておかないと面白くない。 |
|