
東 海 道
|
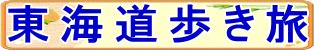 |
36 赤坂宿から藤川宿へ 歩行地図 |
| 関川神社-赤坂紅里-長沢-本宿-山中-藤川 (約10.3㎞ |
|
36赤坂宿
隣の御油宿から16町しか離れておらず、宿の朱印状には「赤坂・五位」と併記され、当初赤坂・御油宿は一宿として扱われていたと思われる。その後下りは藤川から御油まで通し、上りは吉田から赤坂宿まで通し、上りと下りで使い分けられていた時期もあった。御油同様この宿も飯盛女が沢山いて、遊興の宿として賑わっていた。明治以後東海道線が通らないこともあり、衰退して行く。
本陣3 脇本陣1 旅籠62 |
  2008年8月1日御油宿からの続き 2008年8月1日御油宿からの続き
■関川神社~長沢
●関川神社
御油の松並木を抜け、音羽川を渡って赤坂宿に入ると、すぐ左手には「関川神社」が見えてくる。境内には●芭蕉句碑がある。句碑には
「夏の月御油よりいでて赤坂や」
と刻まれているが、この句は、松尾芭蕉が夏の夜の短さと、16町しかない赤坂と御油間の距離の短さを詠ったもの
16:35 |
  ●町並み ●町並み
御油同様人は少ない。明治以後の衰退が大きい。赤坂駅は無人駅ということだ。そんな中でも旧旅籠らしい家は残っているし、宿看板などが出てる。神社を出てしばらく歩くと左手「長福寺」の先に●「問屋場跡」の説明があるが、当時はこの問屋場の向かい側に本陣があったという。脇本陣も本陣も残っていない。但し本陣跡が資料館のようでもあったが、閉館後だったし、時間がなく通りすぎた。 16:40 |
  ●尾崎屋 ●尾崎屋
赤坂紅里交差点手前に、高札場が復元されたようになっており、赤坂宿図も掛けてある。右手角に尾崎屋という商家があった。軒先に行灯型の看板が出ており、現在でも民芸品の製造、販売を行っている。尾崎屋の筋向いに街道筋では有名な●「旅籠 大橋屋」があり、現在でも旅館業を営んでいる。本日は人気がなく、宿泊客がいるようには思えなかった。また玄関先には歴史のあるような提灯が下げられている。大橋屋の説明 |
  先に進み右手に●御休処 よらまいかん」と名付けられた、連子窓のある古い町屋を模した休憩所が出来ていた。ここも時間が無く、入らず先に進む。この右側の駐車場前に「赤坂陣屋跡」の案内板があった。赤坂宿付近は,江戸時代幕府直轄の天領で,三河代官の出張陣屋があった。 赤坂宿の外れ近くの右奥に、●杉森八幡社があった。ここには夫婦楠と呼ばれる楠の巨木がある。ここを過ぎると赤坂宿も終わりとなる。16:55 先に進み右手に●御休処 よらまいかん」と名付けられた、連子窓のある古い町屋を模した休憩所が出来ていた。ここも時間が無く、入らず先に進む。この右側の駐車場前に「赤坂陣屋跡」の案内板があった。赤坂宿付近は,江戸時代幕府直轄の天領で,三河代官の出張陣屋があった。 赤坂宿の外れ近くの右奥に、●杉森八幡社があった。ここには夫婦楠と呼ばれる楠の巨木がある。ここを過ぎると赤坂宿も終わりとなる。16:55 |
  音羽中学を過ぎると民家はほとんど見られない 音羽中学を過ぎると民家はほとんど見られない
この辺りは●「長沢」と呼ばれている集落で、バイパスの下を潜っていくと、「長沢の一里塚」の石碑が立っている。ここで夕方遅くもなり、赤坂あたりではまともな宿がないので、岡崎で泊まることにして、誓林寺を右折して、明電「長沢駅」から岡崎へ出た。「長沢駅」は無人であり、おまけに各駅停車は30分に1本しかなかった。 17:00
2008年8月2日 長沢駅より街道復帰
■長沢~国道1号
やがて左手を流れている「音羽川」が旧道に近づいてくるが、この付近は昔の面影を残す狭い道路がそのまま残っていて、●古そうな家も所々にあり、なかなか風情のある街道だ。途中の観音堂跡には「みほとけ」歌碑がある。8:50 |
  ■国道~本宿 ■国道~本宿
狭い昔ながらの旧道はやがて●国道に合流する。 ここからは現在の国道が旧道で喧噪で面白くない。途中で「豊川市」と「岡崎市」の境を越えるが、越えた先が、赤坂が宿場になる前に宿場だったといわれている「本宿」といわれる。現在の●本宿入口には「東海道ルネッサンス」の立派な碑が作られていて、本宿の詳しい説明がある。本宿は赤坂宿と藤川宿の間にある「間の宿」であった。 |
  ■本宿~山中 ■本宿~山中
●●法蔵寺
本宿に入るとすぐ左側に見えてくる。 ここは徳川家の祖である「松平家」ゆかりの寺と言われ、大宝元年(701)僧行基によって開かれたと伝えられている。奥には松平家の墓が並んでいたので、当時の大名行列はかならず下馬して参詣していったという。境内に入るとすぐに、「草紙掛松」碑があるが、これは家康が幼少の頃、この寺で手習や漢藉を受けていた時、手習の草紙をこの松にかけて乾燥していたからだという。 今ではこの松自体はすでに枯れ、新しい松が植えられている。境内左奥に、新撰組の隊長、「近藤勇」の首塚と呼ばれているものもある。 近藤勇は江戸の板橋で処刑され、首は京都の鴨川に晒されていたが、同士が盗んでここに埋めたと伝わっている。9:40 |
  ●本宿の町並み ●本宿の町並み
本宿は「間の宿」ではあったが、現在では隣の赤坂や御油に比べて人口も多く、名鉄の急行電車も停車し、本宿のほうが賑やかと思う。旧道には本宿本陣跡や陣屋屋敷、味噌工場、などが残る。 駅前のと交差点を越えた所には一里塚跡碑もある。ここを過ぎると、左手に古い●長屋門を備えた家がある。代々医者の宇都野家の遺構である。ここを過ぎると国道に出て、「山中立場」へ向かう |
  ■山中~藤川 ■山中~藤川
●「山中立場」
国道を1km程ほど歩いて、右側への集落下って行った所を「山中立場」といった。途中の右手に名電「山中駅」がある。ここも本宿と同じくらい賑わった立場といわれて、旧街道らしい雰囲気は感じられる。立場外れの下り坂あたりの風景を、広重は行書版「藤川」で描いている。この旧道もしばらくで国道に合流(舞木町西)してしまう。 国道南側に有力な神社があるので寄ってみた。
国道を横断して行くと、奥にひときわ大きな●「常夜燈」があるが、これは「山中八幡神社」の入口を示している常夜燈。 10:35 |
  ● 「山中八幡」 ● 「山中八幡」
「舞木八幡」とも呼ばれている古い神社で、文武天皇の頃(697~)、山中光重という人物が豊前国の宇佐より勧請したと伝わっている。長い階段があって、うんざりするけど、行かねばなるまいとがんばった。この階段の途中には家康が一向一揆(永禄6年(1563)の時に逃げ隠れていたという「●洞窟(鳩ヶ窟)」も残されている。とても小さくい穴で、人が入れるとは思えないので、当時はもっと大きかったのだろうか。 10:45 |
 そんな由来の残る山中八幡を左手に巻きながら、しばらく歩くと再び国道に出る。本来の旧道は、「舞木町西」交差点から国道伝いに右折して、行っていた。。左手に大きな工場が見えてくるが、そこの「市場町」交差点がが旧道入口で、藤川宿の東棒鼻がある。 そんな由来の残る山中八幡を左手に巻きながら、しばらく歩くと再び国道に出る。本来の旧道は、「舞木町西」交差点から国道伝いに右折して、行っていた。。左手に大きな工場が見えてくるが、そこの「市場町」交差点がが旧道入口で、藤川宿の東棒鼻がある。
11:00
藤川宿へ続く。
|
|