
東 海 道
|
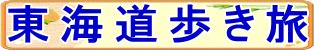 |
31 新居宿から白須賀宿へ 歩行地図 |
| 新居町駅-関所跡-新居宿-橋本-浜名旧街道-元白須賀 4.8km |
|
31新居宿
東海道、日本橋から数えて31番目の宿である。古くは「荒江」、「荒井」と表記されたこともある。舞阪より「今切の渡し」で渡ってくると、新居の関所内へ着岸しなければならなかった。度重なる地震と津波の被害により、関所のみならず宿場そのものが何度か移転している。現在の位置に落ち着いたのは、宝永4年(1707年)。関所の建物が現存し、関所資料館として保存されている。
本陣3 脇本陣0 旅籠26 |
  ■新居町駅~新居宿 ■新居町駅~新居宿
2008年6月8日 8:00 新居町駅より
線路に沿って関所方面へ歩く。線路脇の小公園の中に●山頭火の句碑があった。
水のまんなかの道がまっすぐ 山頭火
●新居関所跡
駅より800m程西よりにある。新居関所は、正式には「今切関所」といい、慶長5年(1600)に設置されました。当初は今切口近くにありましたが、地震・津波により再三被災・移転、宝永4年の大地震により現在地へ移転。 8:15 |
  ●安政2年(1855)に建てられた建物がそのまま保存され、唯一の関所跡として貴重である。関所資料館として開放されている。残念ながら開館が9時であり、時間が無くて外から撮影するだけであった。 ●安政2年(1855)に建てられた建物がそのまま保存され、唯一の関所跡として貴重である。関所資料館として開放されている。残念ながら開館が9時であり、時間が無くて外から撮影するだけであった。
新居関所の東側に堀が掘られ、●石垣と雁木が復元されていた。 浜名湖から渡し船は直接関所へ入っていたので、実際にははるかに大規模だった。 |
  ●「無人島漂流者碑」 ●「無人島漂流者碑」
関所の対面にある。享保3年今切を出航した新居宿の船「鹿丸」が銚子沖で遭難し、無人島の鳥島に漂着。乗組員12人の内9人が死亡、残る3人が都合21年を生き抜いて救助されたという物語。
●新居宿旅籠、紀伊国屋資料館
旅籠紀伊国屋は紀州の出身で、江戸時代のはじめに新居に来て、茶屋を営んだという。はじめは小野田姓を名乗り、後に疋田弥左衛門に改めた。昭和二十四年まで旅館業を営んでいたという。 関所と共に資料館として公開されている 8:25 |
  ●本陣跡 ●本陣跡
飯田本陣跡。飯田本陣には小浜、桑名、岸和田藩など約七十家が利用した。明治元年、天皇行幸の際に行在所となる、
●疋田八郎兵衛本陣跡 飯田本陣の南隣りにあった。建坪百九十三坪で、八郎兵衛本陣には吉田藩のほか御三家など約百二十家が利用した。庄屋、年寄役なども務めた。現在も子孫が居住しているようだ。右手に疋田弥五助本陣跡もあるが医院になっている。 |
  街道は朝早くだったせいか静かなもの、コンビニがあるわけでなく、●旅籠風な古い建物が散見される。スーパーが1軒。西側裏手に●諏訪神社がある。手筒花火で有名だそうだが。中学校へ向う道沿いに参道入口の鳥居が立ち、参道入口には「諏訪神社のケヤキ」という巨木がある。元は景行天皇の時代(西暦89年頃)創建の延喜式内社の猪鼻湖神社とされる。天正10年(1582)武田家滅亡後に来住した山本勘助の重臣の井口嘉末の諏訪大明神勧請により諏訪神社となる。 8:35 街道は朝早くだったせいか静かなもの、コンビニがあるわけでなく、●旅籠風な古い建物が散見される。スーパーが1軒。西側裏手に●諏訪神社がある。手筒花火で有名だそうだが。中学校へ向う道沿いに参道入口の鳥居が立ち、参道入口には「諏訪神社のケヤキ」という巨木がある。元は景行天皇の時代(西暦89年頃)創建の延喜式内社の猪鼻湖神社とされる。天正10年(1582)武田家滅亡後に来住した山本勘助の重臣の井口嘉末の諏訪大明神勧請により諏訪神社となる。 8:35 |
  ■新居宿~浜名旧街道 ■新居宿~浜名旧街道
●棒鼻跡
街道を南へ真っ直ぐ進む。宿の終わり、枡形を曲がったあたりに碑が立っている。棒鼻とは駕籠の棒先の意味。大名行列が宿場へ入るとき先頭を棒先で整えたのでこの場所を棒鼻と呼ぶようになったといわれる。
国道1号へぶつかり、右折する。●左手に古い建物が建っている。このあたり橋本と呼ぶ。かって浜名川に架かる浜名橋のたもとにあったので、橋にちなんだ地名。東海道の要衝としての重要な宿であった。平安時代の古東海道はここから、真っ直ぐに舞坂へ歩いて行けたという。浜名橋の旧跡を探した見たけれど、特にそれらしきものは見あたらなかった。 8:50 |
  ●風炉の井戸 ●風炉の井戸
国道の左手、民家内にある井戸は、建久元年(1190)源頼朝が上洛のおり、橋本宿に宿泊した時にこの水を茶の湯に用いたと伝えられる。昭和五十四年に町の史跡に指定した。
●教恩寺
源頼朝に寵愛された遊女が、頼朝没後に尼となり、妙相と号して、建てた寺院。1300年創建の古刹で、楼門は江戸期のもの。 9:15 |
  教恩寺の先を右折して、旧浜名街道に入る 教恩寺の先を右折して、旧浜名街道に入る
●紅葉寺跡
少し先の右手奥に、「足利義教公富士紀行に入来ありて、風景を愛し、紅葉を賞したまうよりこの名がある」という、寺がある。
荒廃しているという話だったが、行ってみると、石段だけがあり、上って行くと、寺そのものが存在しておらず、ただ原っぱになっていた。脇に●石仏が3基だけ祀られていたのみであった。看板も汚れていて読めなかった。9:25 |
   ●旧東海道の松並木 ●旧東海道の松並木
この街道は昔より東海道として、最重要な道で、江戸時代初期の幕府により、大倉戸から橋本にかけて松が植えられた。しかし松くい虫により全滅したので、近年植栽復原された。道を西に進むと、大倉戸。松並木が切れたあたり「●立場跡の案内板」が立っていた。が案内板をかするように乗用車がデンと駐車しており、案内も読めず、写真も撮れず、大迷惑である。この先だんだんと●連子格子をそなえた、いい感じの建物が現れてきた。 9:45 |
  ●明治天皇野立所阯 ●明治天皇野立所阯
大倉戸の集落を出る手前に柵に囲まれて、昭和11年建立の石碑と木製立札説明板がある。明治元年東京へ行幸した明治天皇が休憩した場所。
●火鎮神社
かつての白須賀宿の鎮守の社。祭神は火之迦具土神、品陀和気命、応永年間(1394~)の津波、安永年間(1772~)の火災で古文書消失し、創建詳細は不明。
さてこの先、元町という地名になるが、そこは津波で流される以前の白須賀宿があった場所で、津波後現在地へ移転した。ここから白須賀宿へと続く。 9:56 |
|